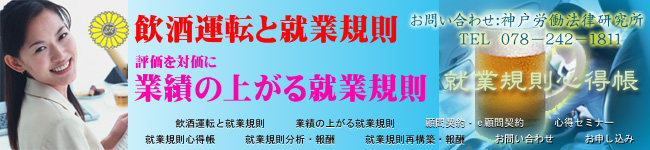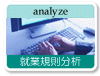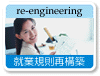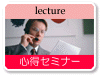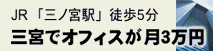飲酒運転と就業規則
飲酒運転・酒気帯び運転による悲惨な事故が後を絶ちませんが、みなさんの会社では飲酒運転が発覚した場合の懲戒規定はキチンと整備されていますでしょうか。
私がこれまで関わってきた運送業や飲食業、食品製造業については、その他の業種よりも飲酒運転について比較的懲戒規定を整備している会社が多くありましたが、就業規則をみてみると、実効性が担保されていない規定であったり、懲戒基準が不明瞭なものが多かったのも事実です。
実効性が担保されていなければ、飲酒運転そのものを会社が把握できないこともままあり、解雇する場合の解雇基準に飲酒運転について規定されていない場合についても、解雇することが非常に難しくなります。無理に解雇して、後々地位確認請求訴訟など提起されてしまうと、非常にやっかいです。
運送業や飲食業、食品製造業でもそのような状況ですから、その他の業種は、何ら対策を講じていない会社が非常に多いです。
このところ、公務員の飲酒運転による事故が多く報道されていますが、公務員は公僕であり、労働基準法の適用を受けません。民間の模範となるべき公務員がそのような事故を発生せしめた場合、免職を前提とした処分は相当程度の妥当性を帯びます。
しかしながら、民間の会社でそのような懲戒解雇処分を下すには、普段から飲酒運転は厳禁であるとか、就業規則にも穴のないよう規定して従業員に周知していない限り、即解雇とするには無理があります。
また、一方で、飲酒運転を幇助した場合の懲戒規定についても綿密に検討されていなければなりません。
幇助と一言でいっても、
幇助と一言でいっても、
- 一緒に酒を飲んで同乗した場合
- 酒は飲んでいないが、同乗した場合
- 車で来たことを知っていて酒を勧める場合
など、そのケースも様々です。これを一括して懲戒解雇処分とするか否かは、当然、当社の実情に合わせて検討しておく必要があります。(ほとんどの会社は検討などしていない!)
ここまで読んでいただいた方はお分かりと思いますが、その検討結果を踏まえて飲酒運転の懲戒措置を就業規則に規定しておくのです。
ご自身の会社の実情に合わせて同業他社とのバランスをとりながら実効性のある懲戒規定を就業規則に盛り込むことで、はじめて飲酒運転をさせない抑止力が生まれるのです。飲酒運転が発覚してしまえば、普段はまじめで優秀な従業員を解雇せねばならなくなります。地位確認請求などする従業員は諦めもつきますが、当社の戦力から離脱させたくない従業員を解雇しなければならないときほど、苦しいものはありません。
速やかに実効性をもった抑止力のある就業規則を構築されることをお勧めします。
飲酒運転に係る法規制
平成13年12月の刑法改正により、人身事故のうち、特に悪質又は危険な運転行為で人を死傷させた場合に、故意犯として重く処罰されることとなりました。参考までに道路交通法の罰則とともに紹介します。
- 刑法第208条の2 危険運転致死傷罪
第1項
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は10年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を死傷させた者も同様とする。
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は10年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を死傷させた者も同様とする。
| 運転行為 |
事故の結果 |
法定刑 |
| アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行 | 人を負傷させた | 1月以上10年以下の懲役 |
| 人を死亡させた | 1年以上15年以下の懲役 |
- 改正道路交通法による罰則
飲酒運転等の悪質かつ危険な運転者が引き起こす重大な死傷事故が多発していることから道路交通法が改正され、次のとおり、罰則がこれまでより厳しくなりました。
| 違反行為 |
法定刑 |
酒気帯び運転 |
1月以上1年以下の懲役 又は30万円以下の罰金 |
| 酒酔い運転 | 1月以上3年以下の懲役 又は50万円以下の罰金 |
| 救護義務違反(轢き逃げ) | 1月以上5年以下の懲役 又は50万円以下の罰金 |
| 運転行為 |
違反点数 |
付加点数 |
| 酒酔い運転 | 25 |
- |
| 酒気帯び運転(0.25㎎以上) | 13 |
- |
酒気帯び運転(0.15㎎以上0.25㎎未満) |
6 |
- |
| 死亡事故 | - |
20 |
| 治療3ヶ月以上の重傷事故等 | - |
13 |
| 救護義務違反(轢き逃げ) | - |
23 |
このように飲酒運転により検挙されたり、事故を発生させてしまえば、相応の社会的責任を取らされることになります。自社のまじめな社員がこのようなことを起こすことのないよう、速やかに実効性のある就業規則の整備を行わなくてはなりません。
就業規則の分析へ
これから就業規則を改訂されるあなたには、当所の就業規則分析をお勧めします。これは、
- 現在の就業規則のままだとどのような状況が予想されるか
- あるいはその状況に対応できないか
- 飲酒運転の抑止力はあるか
- セクハラ対策はなされているか
- 現在の法令に準拠しているか
- 条文と条文のリンケージはとれているか 等
を分析し、その是正方法をご指導差し上げます。詳しくは、「就業規則分析」のページでご案内いたします。